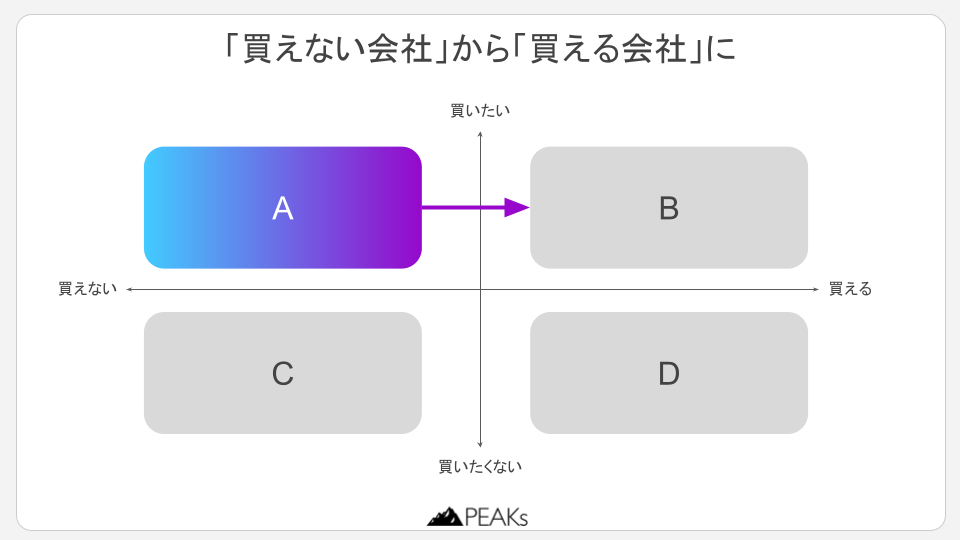会社の売却を検討する際に経営者が最も気になる「うちの会社はいくらで売れるのか?」という点です。
M&Aにおける会社の売買金額(=企業価値)の評価方法についてネットや書籍で調べても、ファイナンス上の難解なロジックや大企業を対象とした手法も多く中小企業のM&A実務には適用が難しい側面があります。
代表的な3つの手法とそれを適用するための実務面も含めて解説します。
DCF法
DCF法は企業価値評価の最も理論的な企業価値算定手法と言われており、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法の頭文字をとったものです。
理論的には「将来稼ぐキャッシュフローを現在の価値に置き換えるといくらか?」という考え方で企業価値を算定しています。
具体的な算定方法は以下の複雑な割引計算を行うことになります。
企業価値 = 1期後FCF/(1+WACC) + 2期後FCF/(1+WACC)^2 + 3期後FCF/(1+WACC)^3 + ・・・
FCFとはフリー・キャッシュフローのことで、企業獲得したキャッシュのことです。逆にいえばフリー・キャッシュフローという名前の通り自由に使える現金を表します。
WACCとは加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital)の頭文字で、会社の資本・負債それぞれにどれだけコストがかかるのかの料率を表します。
例えばある会社が自己資本4000万円、借入1000万円で運営しており株主への配当利回りが10%、借入利率が3%だった場合のWACCは以下の通りです。
WACC = (10%×4,000+3%×1,000)/(4,000+1,000) = 8.6%
中小企業M&AにおけるDCF法の課題
ただし中小企業の企業価値算定にあたりDCF法をそのまま適用するには以下のハードルがあります。
- 信頼性のある事業計画が必要
- 割引率の料率によって企業価値が大きく動いてしまう
- 当事者同士の納得感が得にくい
信頼性のある事業計画が必要
上場企業などでは毎期の業績予想や中経営計画を世間に公表することになり、また業績予想と実績に乖離が生じそうになった場合にも開示義務があるため事業計画を毎期精緻に作成しております。
しかし、中小企業ではそこまで精緻な計画は作る必要がなく、むしろそこにリソースを割くくらいなら事業活動にリソースを当てるべきだと思います。そのためDCF法で利用できるほどに精度の高い事業計画は作っていないケースがほとんどです。
割引率によって企業価値が大きく動いてしまう
WACCの算定ロジックは複雑なため詳細は割愛しますが、そのレートが一意に定まるものではなく、算定者によってかなり値が異なります。そしてこのWACCの差が最終的な企業価値に与える影響は非常に大きいです。以下参考までに毎期FCFが10,000、WACCが10%のケースと11%のケースで5年分の企業価値を比較してみます。
| 経過年数 | FCF | 10%の割引価値 | 11%の割引価値 |
| 1 | 10,000 | 9,091 | 8,190 |
| 2 | 10,000 | 8,264 | 6,708 |
| 3 | 10,000 | 7,513 | 5,494 |
| 4 | 10,000 | 6,830 | 4,499 |
| 5 | 10,000 | 6,209 | 3,685 |
| TOTAL | 50,000 | 37,908 | 28,575 |
料率はわずか1%の差ですが、5年での企業価値は30%以上も開きが生じています。
そのため、DCF法の結果は適用する料率(WACC)の算定にあたり慎重な判断が求められます。
当事者同士の納得感が得にくい
ここまで読み進めていただいてご理解のとおり、将来の事業計画をベースにしたFCFという不確実性と慎重な取り扱いが求められるWACCを用いてDCF法での企業価値算定は売り手・買い手ともに直感的には理解しづらい金額が算出されることになります。そのため当該算定方法での売却価格交渉も難しくなってしまいます。
そこでDCF法以外に中小企業M&Aでよく利用される方法を2つご紹介します。
年買法(年倍法)
年買法(年倍法)とは企業の時価純資産に営業権を加算した企業価値算定方法です。
以下がその計算式ですが、DCF法と比較するとかなりシンプルです。
企業価値 = 時価純資産(A) + 営業権(B)
時価純資産
時価純資産とは全ての資産と負債を時価評価した上で、その差額となる純資産を算定する方法です。会社を今精算したらいくらになるのか?という精算価値と類似する金額になります。
純資産は決算書の貸借対照表(BS)にて算定されているため確定申告書にて確認することができます。これを簿価純資産と呼んだりします。簿価とは帳簿価格のことで「経理の帳簿にいくらで計上されているか?」を意味します。
時価純資産(A) = 時価資産 – 時価負債
実務上はこれに現状の時価と乖離する部分を調整して時価純資産を算定します。
よくある資産及び負債の時価ー簿価差額の調整項目としては以下のようなものがあります。
| 勘定科目 | 調整内容 |
| 売掛金 | 回収不能な債権や滞留しているものは簿価よりも時価が下落しているので、この差額を減額処理する |
| 棚卸資産 | 不良在庫などの商品は時価が簿価よりも下落しているのでこの差額を減額処理する |
| 有価証券 | 株式の価格が取得時よりも値上がりもしくは値下がりしていると時価と簿価が乖離するのでこの差額を加減算する |
| 土地 | 土地の地価が上昇もしくは下落している場合は時価と簿価が乖離するのでこの差額を加減算する。 |
| 未払金や未払費用 | 決算書には計上されていない費用項目の計上もれがあればこれを負債に加算 |
営業権
その企業の「超過収益力を実態収益(経常的に発生する利益)の何年分とみるか」という指標になります。
営業権 = 実態収益 × 年数
実態収益は「企業が実質的にどれだけの利益を稼ぐ力があるのか」を意味します。基本的には損益計算書の営業利益や経常利益と近似しますが、中小企業では経理ルールが各社まちまちなので実態収益力の算定には調整が行われることが多く、以下いくつか例示します。
| 項目 | 調整 |
| 社長の個人的支出 | 交際費や住宅費などでオーナー個人で使用したもので会社の帳簿に載っているもの。当該費用の影響を除く(利益プラス方向) |
| 社長の親族への人件費 | 勤務実態は無いが社長の親族へ給与が払われているもの。上記同様に費用影響を除く(利益プラス方向) |
| 事業外の収益 | 会社で株式投資を行い利益が出たケースなど。利益から控除する(利益マイナス方向) |
| 高額な役員報酬 | 一般的な水準と比較して過度に高額な役員報酬を払っているケースは、一般的な水準まで調整。(利益プラス方向) |
これらの調整を行い企業の実態収益を算定したらそこに年数を乗じることで営業権の価値を算定するのですが、一般的には2~7年分程度のケースが多くなります。
市場やビジネスモデルの影響により年数は変わってきますが相対的に以下の傾向で年数の長短が生じます。
- 成長市場>縮小市場
- 経営者依存度が低い会社>依存度が高い会社
- 毎月安定した収益がビジネスモデル>収益のバラツキが大きいビジネスモデル
- M&Aの買い手が多い業界>買い手が少ない業界
年買法(年倍法)のメリット
年買法(年倍法)のメリットとしては以下の点があげられます。
- DCF法と比較して算出が簡単である
- 時価純資産+営業権(利益の数年分)なので経営者にとって直感的に理解しやすい
年買法(年倍法)のデメリット
年買法(年倍法)のデメリットとしては以下の点があげられます。
- 営業権の算定にあたり何年にするかで客観性が乏しく、恣意性が介入しやすい
- また同様にその年数に論理性を持たせづらい
EV/EBITDA倍率(EBITDAマルチプル)
年買法(年倍法)に次いで中小企業M&Aにおいてよく利用される企業価値評価手法がEV/EBITDA倍率です。これは類似企業比較法(マルチプル法)の一種で、類似する企業の企業価値とEBITDAの比率を用いて企業の価値を算定する方法です。
企業価値 = 当社EBITDA × 類似企業EV/EBITDA倍率 - 純有利子負債
EBITDAが見慣れない指標かもしれませんが、税引き前利益に支払利息と減価償却費を加算するのみなので、決算書から簡単に算定することが可能です。
EBITDA = 税引前利益 + 支払利息 + 減価償却費
類似企業については上場企業で同業の会社を数社探して、時価総額をEVとし、その会社のEBITDAの何倍か?を算定します。
純有利子負債は借入残高から預金残高を控除したものなので、こちらも決算書から簡単に算定することが可能です。
EV/EBITDA倍率のメリット
EV/EBITDA倍率には以下のメリットがあります
- 算定に用いる情報の入手が比較的用意
- 上場企業の企業価値と比較しているので算定根拠の客観性が高い
- 類似の上場企業との比率なので一定の理論的根拠がある
EV/EBITDA倍率のデメリット
EV/EBITDA倍率には以下のデメリットがあります
- 業界や業種で比較企業を選定するため当社個別の事情が企業価値に反映できない
まとめ
中小企業M&Aで用いられる企業価値方法を3つご紹介しました。それぞれの特徴を比較すると下表の通りです。
| DCF法 | 年買法(年倍法) | EV/EBITDA | |
| 算定難易度 | × | ◎ | ○ |
| 理解しやすさ | × | ◎ | ○ |
| 理論的か | ◎ | × | ○ |
| 必要な情報 | 将来の計画 | 過去の実績 | 過去の実績 |
| 客観性 | ○ | × | ○ |
| 企業個別事情の反映 | ○ | ○ | × |
まずは各手法とも基礎となる自社の財務情報の整理から始めてみてはいかがでしょうか?